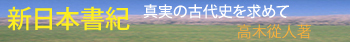漢字音について
漢字音について以下のように考えています。
弥生人が渡来して以来、倭と大陸の民間の交流は途絶えることは無かったのです。国どうしでも奴国と後漢の交流、邪馬台国と魏国との交流、倭の五王と南朝との交流等が有りました。それに伴い、漢字とその音に関する情報を含めて、大陸の情報は絶えず倭国に流入していました。六世紀頃までのそれらの漢字音に関する情報の集成が漢字の呉音として遺されています。その中、南朝の影響が大きかったとしても、南朝は後漢・魏・晋の中心地だった華北の漢人が五胡による混乱を避けて南に移住し江南の漢人と共に建国した国々ですので、それまでの後漢・魏・晋から移入した音が呉音として通用すると考えます。つまり、呉音は五胡に踏みにじられる前の中華の漢字音を保存していると考えます。
また、対馬音は呉音と同一ではありません。対馬音は欽明天皇の時、百済の尼僧、法明が対馬に来て維摩経を読んで漢字の音を伝えたという伝承に由来するのであり、仏教用語に関する音の伝来に限定されると考えられるからです。
これに対し、漢音は五胡の影響を受けた唐の長安の音に由来します。その漢音の情報は七世紀以来の遣唐使等が持ち帰ったものです。漢音が入って来た後、それまでの漢字音の集成にどのような名をつけるかということになり、初めは和音と呼ばれましたが、漢音以前の漢字音の集成は最終段階で南朝の影響を大きく受けたことが意識されるようになりました。その南朝は、中国の呉地方に存在しました。そのため、今までの漢字音の集成は呉音と呼ばれることとなりました。
以上から、「魏志倭人伝」の時代、三世紀にも、完成してはいませんが、倭国には大陸由来の呉音の集成が存在し、「魏志倭人伝」の解読に使用できると考えます。倭の五王関係の中国書籍、宋書等の解読にも呉音が利用できると考えます。そして、「魏志倭人伝」の時代には既に漢字に馴れており、多くはないが訓読みが有ったと考えます。また、日本書紀が成立したのが、720年ですから、既に呉音と漢音の集成が存在し、日本書紀の解読に漢音も利用できると考えます。
魏使は漢字で表記された倭の国名の読みを倭人に漢文で書かせ、原則として、そのままの漢文で報告書に表記しました。呉音が「メ」である「馬」の場合、倭人が訓読みで「ま」として表記し魏使に伝えたものと考えられますが、それもそのまま報告したことから以上のように解せます。
ただし、倭人が「の」の訓読みで報告書に表記した「野」は、魏使が同じナ行の呉音「ヌ」を持つ「奴」に替えて報告しました。「奴」は卑しい者を意味するから倭に対して好んで使用しました。
他方、倭地の官名、人名については、魏使が、教えられて聞いた発音か、その役人や人の印象に基づいて表記しました。ところが、「魏志倭人伝」は次のように述べています。
其地無牛・馬・虎・豹・羊・鵲。
その地には牛・馬・虎・豹・羊・鵲が無い。
(『三国志』巻三十 魏書三十「烏丸鮮卑東夷伝」倭人条、以下「魏志倭人伝」と略す、第二段(15)儋耳と朱崖より)
倭地に馬が無いのなら、なれて生じる馬の訓読みも無かったのではないかという疑問が生じます。しかし、虎・豹・鵲は野生であり通常、飼育されることはありません。牛や馬は家畜とされますが、野生種が存在しました。その牛や馬を野生の虎・豹・鵲と並べて述べています。ここでは、倭地にはいない野生種のことを述べています。そして、倭地には野生の牛や馬はありませんでしたが、家畜として農耕・運搬等に使用される牛や馬は有ったのだと考えられます。因みに鵲は現在の日本では、北海道、新潟、長野、福岡、佐賀、長崎、熊本で繁殖が記録されています。魏使が直接見聞できた九州でも繁殖が確認されていますが、古代にはいなかったか、魏使にはたまたま観察できなかったのでしょう。
因みに、最も古い時代に日本に伝来した古層の漢字音を「古音」と称します。呉音の前に存在したとされる古音の「意」(オ)と「止」(ト)について私の立場から、どう考えるか示しましょう。「意」は「おもい」と訓読みし、その「おもい」の「お」が「意」の読みとなりました。「止」は「とむ」と訓読みし、その「とむ」の「と」が「止」の読みとなりました。古音は、このように訓読みして一部を当てるか、呉音で読めば、済むと考えます。例えば、稲荷山鉄剣銘文の「多支鹵」は古音で「支」を「ケ」と読み「タケル」と読むのが通常ですが、「支」は呉音で「ギ」と読める「岐」の略字で、書かれた時代には「タギル」と読んでいて、「武」(たける)は、「たぎる」と倭語では言っていました。